税理士が明かす!年間30万円得する節税テクニック10選
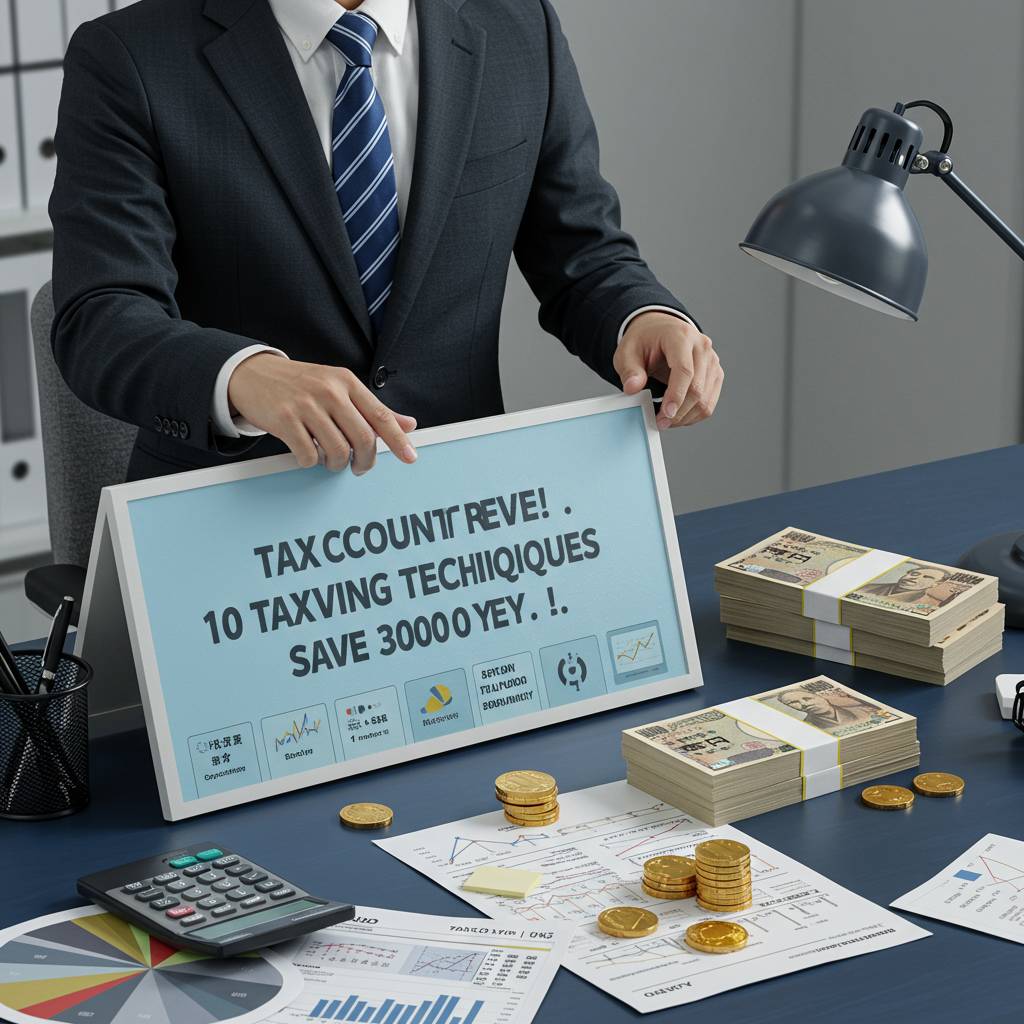 # 税理士が明かす!年間30万円得する節税テクニック10選
# 税理士が明かす!年間30万円得する節税テクニック10選
皆さんこんにちは。今日は多くの方が気になる「節税」について、実践的なテクニックをご紹介します。適切な節税対策を行えば、年間で30万円程度の節税効果が見込める場合もあります。まずは自分に当てはまる方法から試してみましょう。
## 1. ふるさと納税の最適化
ふるさと納税は上限額まで活用することで、実質2,000円の自己負担で返礼品がもらえるだけでなく、所得税・住民税の控除も受けられます。年収や家族構成によって上限額が変わるため、シミュレーションサイトで自分の上限額を確認しましょう。
## 2. iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用
iDeCoは掛金全額が所得控除の対象となり、運用益も非課税です。例えば月23,000円(年間276,000円)を拠出すると、所得税率20%の方なら年間55,200円の節税になります。60歳までの積立で老後資金も貯まる一石二鳥の制度です。
## 3. 医療費控除の徹底活用
年間10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超える医療費は、医療費控除の対象になります。通院交通費や市販薬(医師の処方箋に基づくもの)も対象になるため、レシートを集めておくことが重要です。
## 4. セルフメディケーション税制の利用
特定の健康診断を受けている方は、市販薬の購入費用が年間12,000円を超えた場合、最大88,000円までの控除が受けられます。医療費控除との併用はできないため、どちらが得かを計算しましょう。
## 5. 小規模企業共済の加入(個人事業主向け)
個人事業主や会社役員は、小規模企業共済に加入すると掛金全額が所得控除になります。月70,000円(年間840,000円)まで拠出でき、高所得者なら20万円以上の節税効果があります。
## 6. 経費の正しい計上(事業主向け)
個人事業主や法人経営者は、適切に経費を計上することが重要です。例えば、自宅の一部を事業用に使用している場合、面積按分で家賃や光熱費の一部を経費にできます。ただし、過剰な経費計上は税務調査のリスクがあるため注意が必要です。
## 7. 配偶者控除と配偶者特別控除の使い分け
配偶者の年収に応じて、配偶者控除か配偶者特別控除を選択できます。年収103万円以下なら配偶者控除(38万円)、103万円超201万円以下なら配偶者特別控除(段階的に減額)が適用されます。家計全体の税負担を考えた働き方を検討しましょう。
## 8. 住宅ローン控除の活用
住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、最長13年間、ローン残高の0.7%(上限40万円)が所得税から控除されます。住宅の性能によっては控除期間や限度額が拡大されるケースもあるため、購入前に確認が大切です。
## 9. 生命保険料控除の最適化
生命保険料控除は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3種類があり、それぞれ最大4万円、合計で最大12万円の所得控除が受けられます。家族の保障を考えつつ、税制メリットも最大化しましょう。
## 10. 確定申告での各種所得控除の漏れチェック
源泉徴収だけでは反映されない控除も多いため、確定申告で以下の控除も忘れずに申告しましょう:
- 雑損控除(災害や盗難による損失)
- 寄付金控除(認定NPO法人等への寄付)
- 勤労学生控除
- 障害者控除
- 特定支出控除(特定の職業上必要な支出)
## まとめ
これらの節税テクニックをうまく組み合わせれば、年間30万円以上の節税も十分可能です。ただし、税制は頻繁に改正されるため、最新情報を確認することが大切です。また、自分の状況に合わせた節税対策を選ぶために、専門家への相談も検討してみてください。
節税は違法な脱税とは異なり、法律の範囲内で税負担を軽減する正当な行為です。賢く制度を活用して、家計にゆとりを作りましょう。

